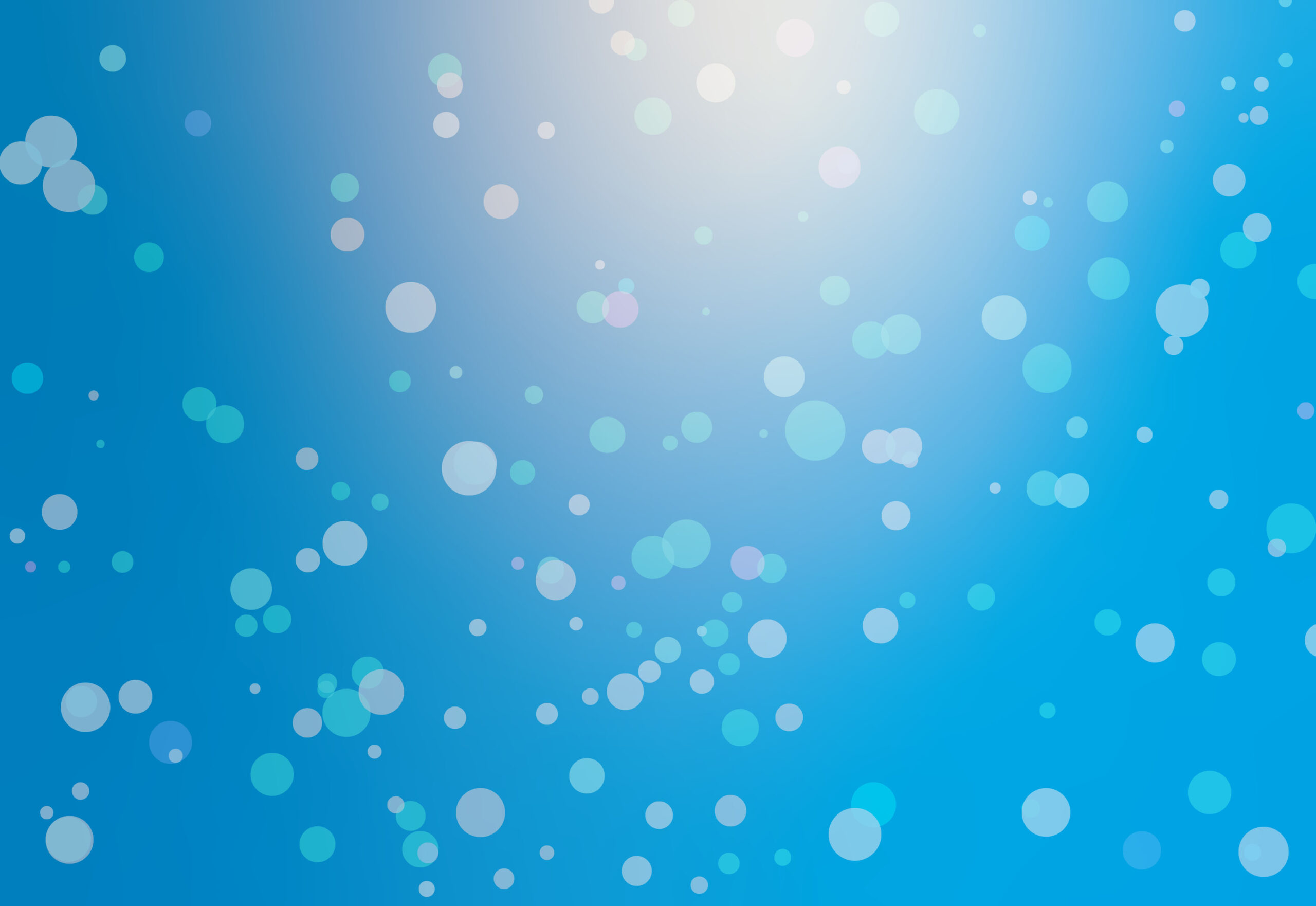幸せを感じるという感覚が、ちょっと前までは本当になかったから、今が信じられない。
呪わしい右手を持って産まれて、地獄のような出来事を経て、絶望しかしていなかった。
だから何であれ、欲しいものなんて手に入るわけもないと思ってた。
もちろん好きな人も……。
単純に、好きな人とはちょっと違うかもしれない。最初はやっかいな絡み方をしてきたただの男で、やっかいな刑事で、でも、俺のことを信じてくれて……初めて、自分から手を伸ばしたいと思った人だった。この右手を「人を救う手」だと言ってくれた人。
でも自分なんかがふさわしいわけもないから、最初から諦めていたのに、彼はずかずかと俺の居場所に入り込んで、居座ってしまった。
俺の葛藤なんか知らずに。
あんまりにも無邪気だから、俺の欲望を知って遠ざかると思っていた。
それが、意外にもあっさり受け入れてくれて、抱きしめてくれて。
嬉しくて本当に幸せで、もう俺は死ぬのかなと思ったんだけど。
夢はまだ続いていて、今もエアコンの効いた部屋で肌を合わせていたりするから不思議だ。さらさらの皮膚が触れている部分から溢れてくる幸せを噛み締めていると、チュンドンは言う。
「なぁ、やんないのか?」
デリカシーがない男なのは最初から分かっている。
俺はただ困って聞き返した。
「やりたいの?」
「いや、俺だって何も好んで尻に突っ込まれたくねぇよ。でもそれじゃおまえが我慢出来ないだろ? だからやろうって言ってんだよ」
「我慢は、出来るよ」
正直に答えた。理性のきかない野獣じゃあるまいし、そのくらいの分別はある。
けれど、そう答えると彼はまた拗ねるのだ。
「あぁー、こいつ、俺みたいなおじさんにはもう魅力を感じなくなったんだな! どうせ俺はくたびれた三十路のおじさんだよ。おまえみたいなきれいな子にはいくらだって」
「何でそうなるんだ?」
俺は本気で呆れる。
俺だって、好き好んで三十半ばのおじさんと寝たいわけじゃない。そんな理屈を超えたところで惚れてるんだ。
バカ正直に言い返すのも恥ずかしくて、黙ってしまう。
「ほら、ローションもゴムも俺が買ってきたんだぞ。どんだけ恥ずかしかったと思ってるんだ。使えばいいだろ」
「わかった、わかったから」
このやかましいおじさんを、俺はかわいいと思ってるから終わっている。
黙っていれば顔は整っているのだが、なんというか、ガサツだ。そこもひっくるめて愛しいと思ってしまっているのは、もう俺が悪いんだろう。
「じゃあ、指だけ挿れてみる?」
「お、よし、やろう」
やっとお互いの妥協点を見つけて、実行してみると、すぐに弱音を上げたのはやはり彼の方だった。
「痛い! 気持ち悪い! 無理、無理だ」
「やっぱり……」
やめとこうと言おうとしたのを、チュンドンが制した。
「……あっ、ちょっと待てっ」
「えっ」
「ん、平気、かも。ちょっと慣れて、ていうか、変な感じが……」
急にモジモジし始めて、顔を赤くするから、俺は驚いた。もしかして、気持ちよくなっている?
唇を噛んで声を抑えようとしているチュンドンが見たこともない顔をしていたので、俺はこのままじゃ抑えがきかなくなるのを感じた。
「今日はここまで!」
そう言って、結局この日は指を一本挿れただけで終了した。
あぶなかった。あのままチュンドンを見ていたら、有無を言わさずに犯してしまいそうだった。
本当に俺は抱き合って眠るだけで幸せなんだけど、わかっていないチュンドンは、落ち込んでいるようだった。
久しぶりに外に出た。
パソコンで絵を描くようになってから、すっかり画材も買わなくなってしまったが、たまにはアナログでも描きたいので、新しい画材やスプレー缶を買いに行った。小さな店が潰れてなくて良かった。
それから近くだったので、麻浦署の前を通ってみた。
そんな都合よく会えるわけではないと思っていたら、都合よくチュンドンが入口から出てきた。
「!」
といっても、向こうは俺に気づかない。
刑事の仲間の、大きな男とじゃれ合って笑っている。
なんというか、距離が、近くないか?
俺と喋るときも近づく距離が近いと思う。いつもドギマギしてしまう。
でも、それはどうやら俺だけじゃないみたいだ。
誰にでも距離が近い、親しげに接する。
それは良いことなんだろうけれど、俺は強烈に嫉妬に駆られた。
よく見れば、大男のほうだって、チュンドンを親しげに見つめているじゃないか。
「くっ」
俺は、警察署に背を向けて歩き出した。
会えるかもなんて期待した俺が馬鹿だった。
あいつにはたくさんの親しい人間がいて、俺にはあいつしかいないことを気付かされた。
それから街で時間をつぶして、夜になるのを待って、気晴らしにグラフィティを描くことにした。
塀にスプレー缶で吹き付ける久しぶりの感覚。
ストレスをぶつけるにはちょうど良かった。
一時間くらい描いてスッキリしたので、家に戻ってきた。
鍵が開いていたので、チュンドンが来ているのはわかったが、部屋は真っ暗のままだ。
「どうしたんだ?」
声をかけながら電気をつけると、俺が入ってきたことに気づいていなかったのか、チュンドンは飛び上がるようにびっくりして、手に持っていたものを慌てて隠す。
「何してたんだ!」
俺はそれを見逃さなかった。
チュンドンが手に持っていたのは、ローションとコンドームだった。
めまいがした。
「誰と使うつもりだったんだ! あの男か?」
大声を上げると、チュンドンはきょとんと目を丸くした。
「え?」
「俺のことなんかもうどうでもよくなったんだろう!」
「ちが、何勘違いして」
「勘違い?」
「これは! 俺が! 一人で練習してたんだよ!」
負けじとチュンドンも大声を出して叫んだ。
「えっ」
その意味がわかるまで、たっぷり二秒はかかった。
「練習……?」
「そうだよ! 悪いか! おまえとちゃんと出来るように練習してたんだ!」
チュンドンの顔は真っ赤で、耳まで赤くなっている。
俺は、自分がとてつもない馬鹿なことに気づいた。
「ご、ごめ……」
「もういい! 何も言うなよ! 恥ずかしいから!」
チュンドンは涙目になって恥ずかしさをこらえているので、俺はどうしようもなくなって、何か言うかわりに抱きしめた。
「ひぇっ、変なところ触るなよ!」
乳首を触ったら怒られた。
「変って……感じてるくせに」
「感じてない! 男がそんなとこで感じるわけないだろう!」
「そう?」
「あっ」
また触ったらチュンドンは裏返った声を出して、真っ赤になって俯いた。
もしかしてこの人は、案外感じやすいのかもしれない。
かわいい、と言いたいのをこらえて、俺は乳首を触り続けた。
「あっ、あっ、だ、だめだって。やだっ」
やだと言ったのでぱっと手を離した。嫌なことはしたくない。
それに気づいて、チュンドンは小声で付け加えた。
「い、嫌じゃない、ほんとは……っ」
自分で言っておいて、また真っ赤になってしまう。
忙しいひとだなぁ。
俺はだんだんこの人のペースに慣れてきたので、落ち着いていられた。
「じゃあ触らせてよ」
「あ、うん……」
大人しくなったので、ちゃんと勃起しているペニスを扱いてあげた。
「あっ、あっ、んっ、ちょっ、早っ、出ちゃ」
「出しちゃっていいよ」
「お、おまえはっ」
「俺は、挿れるから」
「えっ、あっ、出……っ」
チュンドンは射精して、一瞬のけぞった。精液が腹に跳ね跳んだ。
「……はぁ、はぁ」
「大丈夫か?」
「大丈夫、ってうわぁ」
片方の足首を持って転がしたら、チュンドンはベッドの上にひっくり返った。
そのまま、脚の間にもう片方の手を伸ばす。尻の穴にローションを塗りつけた。
「う、うわ」
「平気だろ、こんくらい」
「だ、だけど」
動揺するチュンドンをよそに、俺は覚悟を決めていた。
指を差し入れて、ゆっくり中に埋めていく。
「う……」
中は熱くて引きちぎられそうだ。
「力抜いて、呼吸して」
「はぁ、はぁ」
チュンドンは従順に俺の言葉に従う。
指を挿れて、中の壁を指の腹で触るように動かすと、彼は腰を震わせた。
「ふわっ、変な、感じがっ」
「気持ちいいんだろ?」
「ちが、……くないけど……」
曖昧なことを呟いている間に、俺は指を増やす。二本挿れてまた中を撫でる。
「……ふっ、うぅっ、変に、なるっ」
「もういいかな」
俺は指を引き抜いて、ガチガチに固くなっているペニスをかわりに差し入れた。抵抗を感じるけれど、ゆっくり捩じ込む。
「ひ」
指とは違う圧迫感があるのだろう。チュンドンは一瞬体を固くして、俺が言ったことを思い出したように呼吸を深くし始める。
「うん、そうだよ。大きく息吸って、吐いて」
息を吐いたところで、奥まで突き入れた。
「ひぁっ」
チュンドンは苦しそうな声を上げたが、衝撃に驚いているだけのようだった。
「大丈夫そうだね」
俺も我慢ができないので、浅く腰を動かし始めた。すると途端にチュンドンは喘ぎ始めた。
「あっ、あっ、あっ、はっ、んっ」
俺が奥を突くたびに声を漏らさずにはいられないようだった。
「ひっ、こ、これっ、変っ、あんまりっ、揺する、なっ」
「ごめん、我慢できないっ」
「えっ、あっ、あっ、いや、だっ」
「嫌か?」
慌てて自分を制御しようとするが、止まらなくて、チュンドンはいやいやと首を振った。
「ちが、だいじょうぶっ、いやじゃ、ないっ」
「ほんとに?」
「ほんと、だっ、あっ、きもち、いいっ、いいっ」
練習の成果なのか、チュンドンはひどく感じているようだった。
ペニスは萎えたままだ。体の中で、快感を感じているんだ。
「チュンドン、す、好きだっ、俺っ、あんたがっ」
「あっ、あっ、俺、もっ、ジュン、ジュン……っ!」
俺は耳がキンとして、自分が射精したことに気がついた。
すると、チュンドンも体を硬直させた。
「あっ、うっ、あぁ――――っ」
射精はしていない。後ろだけでイッた?
チュンドンが手足いっぱいにしがみついて来たので、表情を見ることはできなかった。
「だ、大丈夫……?」
「ん、うん……、う、びっくりした」
自分でも、イッたことにびっくりしたらしい。
「俺も」
「こ、こんなおじさんを抱いたこと、後悔してないか?」
何言ってるんだと思った。
「あんた、ばかか? 俺が今どれだけ幸せだと思ってんだよ」
「幸せか? そりゃ、良かった」
そう言ったと思ったら、全身の力が抜けて、ベッドの上にぽすんと沈み込んだ。
「お、おい。本当に大丈夫か?」
「ん、眠い、だけ――――」
眠ってしまった。
残された俺は、その夜、一人でこっそり泣いた。
俺は買ってきたばかりの画材で、久しぶりにキャンバスに絵を描いていた。
「男前に描けよ?」
モデルのチュンドンはちょくちょく動くので、集中するのが難しい。
「動かないでよ」
「えー? 動いてないって」
「動いてるよ」
言い合って、笑い合った。
こんな些細なことが嬉しくて、これからの人生が楽しくなる予感で胸がいっぱいになっていた。
おしまい